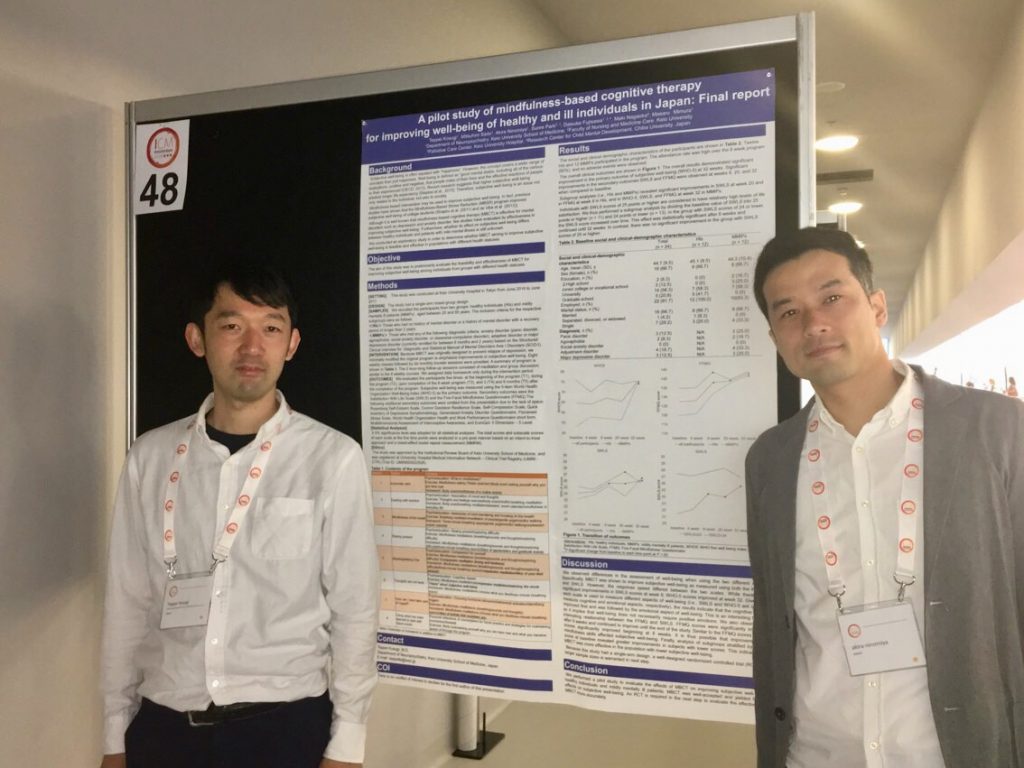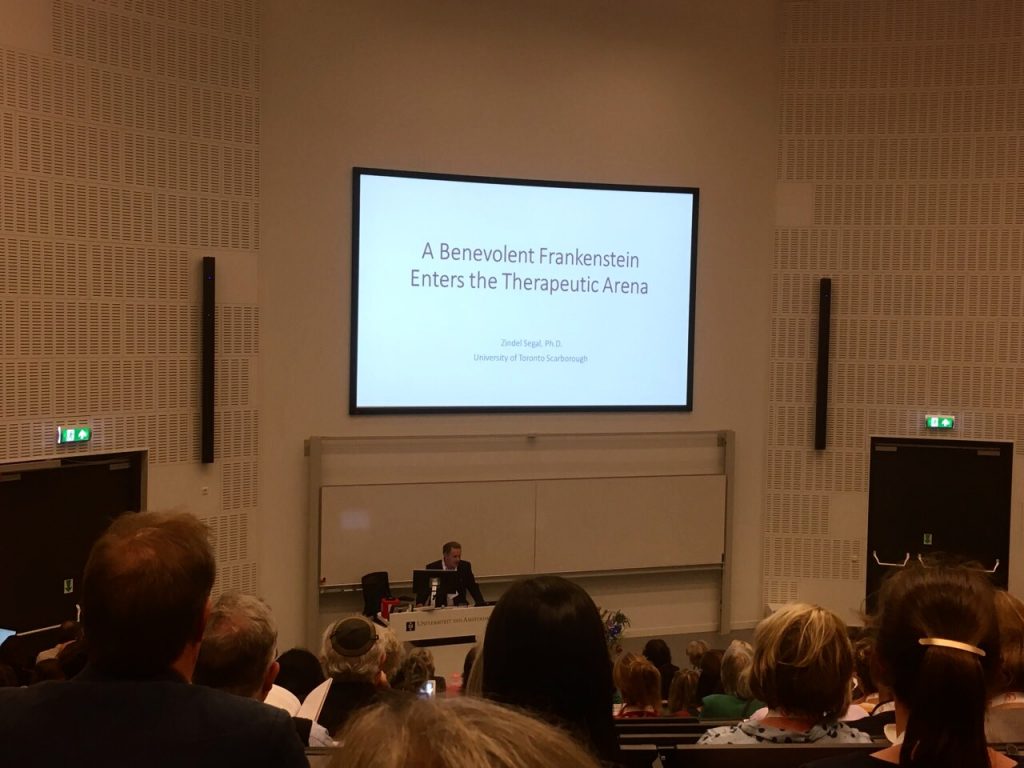マインドフルネス国際学会《International conference on Mindfulness》に参加して
2018年7月11日〜13日、マインドフルネスの国際学会《International conference on Mindfulness》が、オランダのアムステルダムで開催されました。世界中から1,000人近い参加者が集い、臨床適用、効果メカニズム、社会、哲学、および仏教心理学など、さまざまな側面から多くの議論が活発に行われていました。
その中から、ポスター発表と2つの基調講演について報告いたします。
《ポスターセッション》
慶應義塾大学からは、不安障害の無作為比較対照試験の結果、ウェルビーイングのパイロット研究の結果、おなじくウェルビーイングの無作為比較対照試験のプロトコールの3つの演題を発表いたしました。このうち、不安障害の発表はBest presentation awardにノミネートされ、プレゼンテーションの機会もいただきました。残念ながら受賞は逃しましたが、他国の研究の現状や進捗を把握できる、貴重な機会となりました。
《基調講演 Mindfulness: keeping our balance》
-オクスフォード大学名誉教授 マーク・ウィリアムス
学会最終日には、オクスフォード大学の名誉教授、マーク・ウィリアムス氏が、“Mindfulness: keeping our balance”のタイトルで講演を行いました。講演の内容は、「マインドフルネス認知療法開発の経緯」から「マルチタスクがいかに脳に負担をかけるか」まで、幅広い内容を簡単なエクササイズも交えながら発表しました。
ここでは、その講演を振り返りながら、筆者の感想をつづることにします。
「建築家は、自身が設計したショッピングモールのオープン初日に何を観察するのか」という問いかけから、ウィリアム氏の話は始まりました。彼によると、建築家が見るのは、壁が落ちていないか、階段に不具合がないかといった建物の「構造」ではありません。お客がスムースに行き来しているか、吹き抜けに掲げられた掲示板がきちんとお客に必要な情報を伝えられているか(掲示板がお客に情報を届ける役目を果たしているか?)、お客が必要な場所にたどり着き、求めるものを手に入れられているかといった「機能」なのだそうです。つまり建築家は、設計した建物という構造が、それを通して得られるはずの機能をきちんと果たしているかどうかを確認しているのです。このことから「構造とは、本来の目的が機能することを可能にするためのフォーム(形)である」ということ、また「機能の観点から綿密に練り上げられたものである」ということがわかります。
ご存知の方も多いかもしれませんが、マインドフルネス認知療法やマインドフルネスストレス低減法にはカリキュラムがあり、どのクラスで何を行うかが明確に規定されています。ですから、これらのプログラムにはしっかりとした「構造」があると言えます。そしてカリキュラムは、プログラムが意図する明確な「機能」をもとに作り上げられたものでもあります。このことから、カリキュラムの意図をしっかりと理解した上でその構造を守ることが、プログラムのもつ機能を最大限発揮することに繋がります。
しかし、その構造を守っていれば、いつでも意図する機能を果たせるかというと、必ずしもそうではありません。その例としてウィリアム氏は、2つの事例を挙げました。
一つは、「パニック障害の患者さんが、呼吸に注意を向けた瞑想をしている時に、苦しくなることがある」という事例です。パニック障害の方は、突然動悸が激しくなったり、過呼吸を起こしたりして不安がひどくなることがあります。こうした患者さんは、呼吸や胸に注意を向けると、場合によっては過去の体験が呼び起こされてかえって不安が高まってしまいます。そうした時に、呼吸に注意を向けることの本質が「いつでも戻ってこられる錨(いかり)のような役割」であることを理解できていれば、何もその場所を呼吸に限定する必要がないことがわかります。そしてそのまま呼吸に注意を向け続けてもらうのではなく、手や足など体の別の場所に注意を向けるという、構造の修正も可能になることを伝えてくれました。
また二つ目の事例として、マインドフルネス出産育児プログラムを挙げていました。このプログラムは、妊娠中や出産間もない親を対象にしたマインドフルネスのプログラムです。当初は、こうした両親に対してマインドフルネスストレス低減法が実施されていましたが、途中で参加を止めてしてしまう参加者が多くうまくいかなかったようです。そこで、プログラムを妊娠、出産、子育てなどにより焦点を当てたものに修正したところ、うまくいくようになったとのことでした。マインドフルネス出産育児プログラムはマインドフルネスストレス低減法の構造を「修正する」ことで機能が発揮されるようになったよい事例であるとのことでした。
このような例を踏まえて彼は、「マインドフルネスストレス低減法やマインドフルネス認知療法の構造を“修正”して実施することは可能か?と聞かれれば」と述べたあと、少し間をとり、「『それは可能だ』と答えるだろう」と言葉を選ぶように語りました。と同時に「しかし、それはマインドフルネスストレス低減法やマインドフルネス認知療法のDNA(本質)が何であるかを、十分に理解していることが前提だ」とのコメントを強調することも忘れませんでした。
これは、構造の修正は、あくまでマインドフルネスの本質を機能させるために行うべきであり、本質を理解しないままでの修正は、本質を毀損しかねない、ということを意味するものと筆者は考えました。
プログラムの構造を「守ること」、臨機応変に「修正すること」。どちらも大事な対応です。しかし、そもそも「構造」とはいかなるもので、またこれを修正するということが何を意味するのか、どちらの方法を選択するにしても、そうした問いを自問し続けることの重要性を、改めて指摘してくれる内容でした。(文・佐渡充洋)
《基調講演 Benevolent Frankenstein Enters the Therapeutic Arena》
-トロント大学教授 ジンデル・シーガル
2日目にはマインドフルネス認知療法の開発者の1人、ジンデル・シーガル氏の講演がありました。
Benevolent Frankenstein Enters the Therapeutic Arena(慈悲深いフランケンシュタインが治療の場に入り込む)というタイトルからは、講演のテーマが想像できず、はじめはとまどいました。結局のところ、このタイトルは今までの医療にとって異質なものである「瞑想」が持ち込まれたことの比喩だったようです。シーガル氏は開発経緯について詳細に話すとともに、メインのテーマである「どのような“要因”がマインドフルネスの効果をもたらしているのか」についてお話されました。以下、シーガル氏の発表のなかで、特に興味深かった内容に触れることにします。
シーガル氏は、彼自身が研究に関わった、うつ病の再発予防の介入としてグループ認知行動療法とマインドフルネス認知療法を直接比較したRCT研究を紹介しました。そのなかで、グループ認知療法群とマインドフルネス認知療法群の参加者の脱中心化に着目した分析を行なっています。その結果、脱中心化のスコアが大きく改善した群と、改善しなかった/あまり改善しなかった群の2群に分けると、脱中心化のスコアの改善度合いの高い方がうつ病再発率は低く、両群間で再発率に大きな差があることを見出しました。
この研究においてシーガル氏は、参加者がホームワークに取り組んだ時間数も集計しています。結果は、両群ともにほとんど練習を行わない群が最も多く、多くの参加者が期待するほどの練習を行っていないことが明らかとなりました。また同時に、「練習量・脱中心化の改善度合い・再発率」の3者の関係について、「練習量」と「脱中心化の改善度合い」、「脱中心化の改善度合い」と「再発率」との間には有意な相関があるものの、「練習量」と「再発率」との間には、有意な相関が得られなかったことを提示しました。つまりシーガル氏は、うつ病の再発を防ぐためには、ただやみくもに練習すればよいのではなく、いかに脱中心化を促す練習を行うかが重要であることを示したのです。
そして、そのためのヒントとなるよう、筋力トレーニングによる介入の論文を提示しました。その論文では筋力トレーニングによって有意にうつ症状は改善する一方で、練習量や筋力の向上との間には有意な関係性が認められませんでした。ここからシーガル氏はむしろ適度な量を日々継続して行うことが重要ではないかという仮説を導きます。そして同様に、マインドフルネスの練習も量の問題ではなく、適切な形で継続的に行うことが重要なのではないかという仮説を、彼は提示しました。
最近ではマインドフルネス認知療法の作用機序に関する関心が高まり、様々な論文が発表されています。そのなかでも、シーガル氏が示した仮説は今後マインドフルネス認知療法のプログラムに活かしていくことが現実的に期待される実行性のあるものであり、非常に興味深いものでした。またマインドフルネス認知療法の開発者が、昨今のマインドフルネスブームに満足することなく、飽くなき探求心を持ち、マインドフルネス認知療法のプログラムをより有効なものにしていこうとしていた姿勢に非常に刺激を受けた講演でした。(文・二宮朗)